|
二月十三日(その2)
ユキさんちでHR君と言う文化人類学という学問をやっている大学院生に会う。この学問自体歴史が浅いみたいで、どのレベルの視点で捉えるべきなのか漠然としているようだ。彼はこのことについて悩んでいた。文化人類学とは文字の通り「文化を人類という壮大な視点から見る学問」らしい。今までの文化を語る学問は、生活様式や道具等を視点にしていたがこの学問は人間そのものを取り上げるらしい。
すると堀下げていけば、また実際に調査(フィールドワーク)を行おおとすると、一個人の行動や考え方まで、さらには無意識の中まで入っていってしまう(調べないとならない)。しかし、個人を取り上げたのでは文化ではない。ではどうすれば良いのか。僕は聞いてみた「お偉い先生達の論文はどんな感じなの」。彼の答えは「それがマチマチ。だから同じ地方についての論文でも違う印象を持ってしまうこともある。とにかく歴史の浅い学問だから。」と半分あきらめ気味である。しかし前向きな悩みであることは確かだ。聞いていて嫌な気にはならない。あきらめ気味の彼に「じゃあ、君が思った通りに論文書けばいいじゃないか。だって決まりや常識みたいなものは無いんだろう。」と考えることを諦めさせるようなことを彼に言った。かれも「そうですね」と妙に納得したようだった。
今朝、小便をするときに便所ガニがいないのに気がついた。夕方、時間が半端になったのでウチに戻り洗い物をした。洗い場(=お風呂)に便所ガニがいた。目が合った時は驚いて身を引いてしまったが、すぐに「オウ」と挨拶を交わした。
考えてみれば入り口でよく小便をする。寒いときには流しの所でも小便をする。便所ガニとは小便をする所に居座るカニのことのようだ。
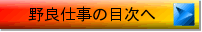   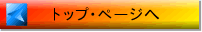
|