|
1月20日(その3)
一通り話が済むとNSさんとその家へと行く。中を簡単に説明してもらい、その日はNSさんと別れた。
この家というのは東京の感覚で言えば「小屋」である。広さはそこそこあるが、軽ブロックで壁を作り、角材で梁を張り、トタンの屋根を乗せている。床は地面より2〜30Cm高く作ってある。三分の二ぐらいには畳も敷いてある。まあまあの作りであるが、窓や戸の立て付けが悪くすきま風が入ってくる。不思議と言っては失礼だが、この家には30インチぐらいのテレビと応接セットがある。ソファーも一人用が二つと長椅子が一つ、とちゃんとセットになっている。正直に言ってこれを見た時、「不思議」とか「異様」とか思った。これは明らかにナイチャー(内地の人間、つまり沖縄の人間ではない、の意。)の偏見であった。さらに炊飯器も電器で電気ポットもある。
風呂と呼ばれる場所は土間にある。この地方で風呂と言えばシャワーのこと。湯船につかる習慣は無い。土間にコンクリートを打って、そこにシャワーをつけただけである。しかし、ここは湯沸かし器が付いていて温水が出る。この地方では水シャワーが一般的なようで、民宿でもお湯の出ないところがあるという噂を耳にしたことがある。ちなみにこの島の宿泊施設では湯船は無いと思った方がよい。歴史的背景から、この島には宿泊施設が多い。その中で湯船があるのは一つか二つだろう、と言っていた人もいた。ちなみに私が年末に泊まったホテル(?)にはユニットバスがあった。
お風呂の話はこれぐらいにして、次はトイレだ。トイレは外にある。大きさは国会議員さんの家の前のポリスボックスを一回り大きくしたぐらいだ。一辺は1m位で入り口は60Cm位であろうか。入り口の戸は壊れていて閉まらない。勿論電器など付いていない。この時もう暗かったので中に入るのをやめた。
一度久野さんの所へ戻り、郵便で送った自分の荷物を持って、その家へ再び戻った。まず、荷物を広げてみた。久野さんが「足りない物があれば言って、貸してあげるから」と言ってくれたので、何が足りないか考えてみた。思いついた物は、夜トイレに行くための懐中電灯だった。他には思いつかない。
久野さんの所へ戻り、懐中電灯を借りたいと伝えると、出てきた物はとても強力で普通のライトに加えて蛍光灯まで付いていた。これならトイレに落ちることはないだろう。
夜、荷物を落ち着かせた後に、このライトを持ってトイレの中を確認したところ、便器はなくコンクリートの床に長方形の穴が開いているだけだった。穴を見つめていると吸い込まれそうになってしまい、これからの生活に少々の不安を覚えた。
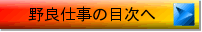   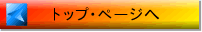
|